|
|
|
|
富山地方鉄道
Toyama Chiho Railroad
富山地方鉄道はその名の通り、
富山を起点とする私鉄です。
宇奈月や立山に路線を広げています。
富山市内にも路面電車を走らせているし、
特急電車を宇奈月温泉まで走らせていて、
中小私鉄の雄のような存在感があります。
鉄道線の営業キロ93.2km、軌道線6.4kmの
計、99.6kmの路線を有しています。
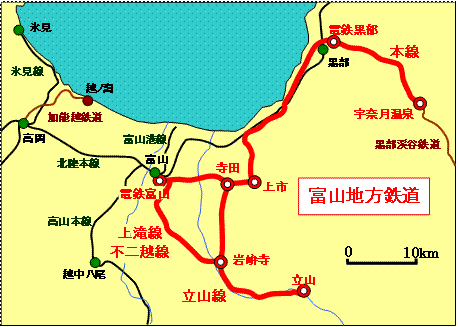
そんな富山地方鉄道の各線を
紹介していこうと思います。
本線
立山線 Jun.19, '10
不二越・上滝線 Dec. 16, '24
軌道線「本線、支線」 NEW! Feb. 05, '25
軌道線「富山都心線」 Apr. 03, '15
富山港線(富山ライトレール) Oct. 29, '06
|
|
|
|
本線
(電鉄富山 - 宇奈月温泉)
Fujikoshi, Kamitaki Line
(Dentetsu Toyama - Unaduki Onsen)
乗車日:Nov. 20, 2007
富山地方鉄道の本線は電鉄富山駅と
宇奈月温泉駅を結ぶ53.3kmの路線です。
富山地方鉄道の前身、富山電気鉄道が
1931年(昭和6年)に富山田地方 -
上市口間を開業したのが始まりで、
その後、立山軽便鉄道や黒部鉄道の路線を
買収し、宇奈月までレールが繋がったのは
1940年昭和15年)だったようです。
富山地方鉄道の立山線には1995年1月に乗車しましたが、
この本線の寺田 - 宇奈月温泉43.5kmは
長い間、未乗区間として残っていました。
その未乗区間も2007年11月20日に乗る機会を得ました。
その時の様子を紹介します。
電鉄富山 - 上市
富山地方鉄道の電鉄富山駅は、
JRの富山駅の東に位置しています。
到着した電車から大勢の通勤客が
改札を抜け、その流れと逆らうように
ホームに向かいました。
8:24発の宇奈月行きは
既にホームに停車中でした。
オレンジと緑色の2両編成の電車が宇奈月行きです。
電鉄富山を発車してすぐの駅構内の様子です。
写真左端の線路は、JR北陸本線です。
以前は、JRの特急列車が富山地方鉄道に
乗り入れていましたが、今は運行されていません。
まだレールは繋がっているようなので、
便利な直通列車の運転を復活して欲しいものです。
そのJR北陸本線と分かれ、
富山の市街地を走ると稲荷町です。
ここは岩峅寺に向かう、
不二越・上滝線との分岐駅です。
稲荷町からも富山の街中の景色が続きます。
東新庄で上り列車と交換すると、進行前方に
立山連峰の山々が見えてきました。
住宅の密集度合いが少なくなったな
と思ったころ、越中荏原です。
線路際にススキの穂がなびき、
車窓前方には、常願寺川の堤防へと
勾配が続いているのが見えました。
勾配を上り、渡った常願寺川です。
この常願寺川を渡ると、田圃が広がり、
その向こうに立山連峰の山々が
聳えているのが見えました。
山頂付近に若干雲が掛かっていますが、
雪を抱いた剣岳や立山が
見えていることと思います。
この素晴らしい景色を眺めるうちに
寺田に到着しました。
ここでも上り列車と交換です。
寺田駅のホームからも
立山連峰を眺められます。
上り電車の到着が少々遅れ気味だったので
しばらく立山連峰を眺めていました。
この寺田駅は立山線との
分岐駅でもあります。
立山線の乗車記はこちらです。
宇奈月温泉からの帰りに、
立山行きのアルペン号に遭遇しました。
この車両は、元西武鉄道のレッドアロー号の車両です。
この風光明媚な富山地方鉄道で第二の活躍の場を
与えられて幸せ者だと思います。
新しい車両となったレッドアロー号の乗車記は
こちらです。
寺田から5〜6分程走ると、
上市に到着しました。
この上市は行き止まり式のホームで
ここで、何人かの乗客が下車し、
進行方向も変わります。
上市 - 電鉄黒部
上市で車内が空き、のどかな雰囲気が漂います。
車窓右手には、ずっと立山連峰の眺めが見えています。
上市まで、ほぼ東を向いて走っていたのですが
折り返した後は、進行方向を北向きに変えています。
天気のいい日にこの路線に乗ることが出来、
本当に良かったと思います。
立山連峰、大日岳の麓から
流れ出た上市川を渡りました。
朝日を浴びて輝く川面の
向こうに立山連峰の山々。
この路線は心行くまで立山連峰の
姿を堪能させてくれます。
上市から2駅目の中加積駅で
上り列車と交換しました。
朝の通勤時間帯にかかる時間だった為もあり
列車交換の頻度も高くなっていますが、
富山地方鉄道本線の運転本数は比較的多く、
立山線の列車の乗り入れる寺田までは日中でも
一時間に約5本、上市まで約4本、そして
上市から先、電鉄黒部までは一時間に3本運行されており
地方のローカル線としては利便性の高い路線です。
中滑川からは再び、進行方向を東にとり、
JR北陸本線と併走するようになります。
越後湯沢行きの特急「はくたか3号」が疾走して行きました。
長い間、立山連峰の眺めを楽しんでいましたが、
立山連峰の山々は次第次第に前衛の山々の
影に隠れるようになります。
今度は、車窓左手遠くに富山湾が見えてきました。
滑川、魚津そして黒部と都市が続き
家も建て込んで来ました。
剱岳に源を発した早月川を渡りました。
この先で、JRの線路をくぐり、
北側を走るようになりました。
西魚津駅で列車交換のため、
しばらく停車です。
鄙びた西魚津の駅舎です。
この小さな駅に、下車した女の人の様子です。
西魚津を出ると、JRと併走し高架橋を走り
魚津の町並みを見下ろすようになります。
田圃の向こうに広がる立山連峰の
山々を見てきた後なので、魚津が
とても都会のように感じます。
電鉄魚津の駅の様子です。
高架の線路に似つかわしい、
少々くたびれた感じの駅舎でした。
車窓右手遠くに白い雪を
被った山が見えてきました。
後立山連峰の白馬岳でしょうか?
朝日岳でしょうか?
このあたりは、立山連峰や後立山連峰の
ほぼ真北に位置するようになり、
山の様子も随分と変わってきました。
JRの線路をオーバークロスすると電鉄黒部です。
電鉄黒部 - 宇奈月温泉
歴史を感じさせるような
電鉄黒部駅のホームの様子です。
電鉄富山から電鉄黒行きの区間列車が
設定されているので、折り返し運転が
出来るような駅の構造になっているようです。
停車中の電車は 9:28 の電鉄黒部始発で、
この列車が到着すると発車していきました。
電鉄黒部からは再び、
のどかな景色が広がりました。
紅葉した木々や柿の赤が
青空に映えていました。
BR>
電鉄黒部駅から4つ目の下山駅の様子です。
富山地方鉄道にはこうした趣の
ある駅舎がいくつも残っているようです。
黒部川の作る扇状地をゆっくり走ります。
行く手に後立山連峰の山々が見えて来ました。
線路際にはススキ野原が
広がるようになりました。
日の光を浴びて輝くススキの穂が綺麗でした。
野原に輝くススキの穂が揺れる景色は
昔はどこにでも見られた光景だと思うのですが、
なんだか久しぶりに見たような気がします。
ススキの穂を眺めるうちに、周囲には山が迫り、
いよいよ黒部川の渓谷に足を踏み入れて行きました。
黒部川の作る渓谷です。
この川を遡っていくとあの
黒部渓谷へと続いています。
黒部川沿いの山々が次第に高く、
渓谷が険しくなるうちに
宇奈月の温泉街が見えてきました。
いよいよ終着・宇奈月温泉駅に到着しました。
電鉄富山から53.3km、1時間34分の旅でした。
富山地方鉄道本線は、思っていた以上に
景色のすばらしい路線でした。
写真左が電鉄富山から乗車した普通電車、
右側が帰路に乗った「特急アルペン」号です。
宇奈月温泉では一時間程の待ち合わせで
黒部峡谷鉄道に乗り、欅平駅に向かいました。
黒部峡谷鉄道の乗車記は
こちらです。
宇奈月温泉の様子は
こちらです。
立山線
(富山 - 寺田 - 立山)
Tateyama Line
(Toyama - Terada - Tateyama)
乗車日:Jan. 30, 1995, Oct. 11, '08
富山地方鉄道立山線は、寺田から
立山黒部アルペンルートの玄関口
立山に至る24.2kmの路線です。
初めて立山への路線に乗ったのは、
1995年の1月末。大雪の1日でした。
その時はあまりにの大雪で、
電車の前方から、墨絵のような
雪景色を眺めていました。
終着の立山駅も、雪に埋もれていました。
この時の立山線の乗車記はこちらです。
この立山線に、2008年10月に
再び乗車する機会を得ました。
その時の様子を紹介します。
金沢からの特急「しらさぎ」を富山で降り、
16:01の立山行き普通電車に乗りました。
特急「しらさぎ」の乗車記はこちらです。
二両編成のツートンカラーの電車が
電鉄富山駅の4番線ホームに停車していました。
土曜日の夕方近い時間帯で、
車内はよく空いていました。
ホームの片隅には、特急や急行の
行き先表示板が置かれていました。
錆付いてはいますが、今も
使われているものです。
発車前の先頭車両からの眺めです。
左側の信号機が青に変わると
定刻に発車しました。
電鉄富山から寺田までの9.8kmは
宇奈月へと向かう本線を走ります。
電鉄富山を発車し、しばらく並走していた
北陸本線と分かれると、不二越・上滝線との
分岐駅・稲荷町駅に到着しました。
留置線の向こうに短い不二越・上滝線の
ホームが見えていました。
稲荷町を発車し、いくつか小駅に停まると
常願寺川を渡りました。
この日は朝から雨が降り、
雲が低く垂れ込めていました。
常願寺川を渡った最初の停車駅の
越中三郷です。
ここも小さな駅です。
錆付いた駅名標と、広告が一枚も入っていない
広告スペースが侘しさを募らせます。
越中三郷の二つ目の駅が寺田です。
寺田駅到着の直前で、左に宇奈月へと
向かうレールが分かれて行きました。
寺田着、16:17です。
反対側のホームには、立山発宇奈月行きの
特急「アルペン」が停車していました。
特急「アルペン」は4月から11月の多客期に
平日1往復、土曜休日に2往復走っています。
寺田に5分間停車し、ここから
立山線の線路を走っていきます。
先頭車両からの前方の眺めです。
常願寺川の造る扇状地の平地を
緩やかに上りながら山間を目指しました。
曇ってはいましたが、車窓左手遠くに
立山連峰の山並みが見えていました。
のどかな富山平野を走り、寺田から
6分ほどで五百石駅に到着しました。
立山町の中心駅で、
上り列車と交換しました。
五百石からものどかな景色の中を走りました。
屋敷杜に囲まれた農家が点在し、
日本の原風景のような光景です。
冬の短い日が既に西に傾いて
空の端が仄かにピンク色に染まっていました。
どんより垂れ込めていた雲が
急に薄くなってきたようです。
のどかな富山平野が尽き、
岩峅寺駅に到着しました。
この岩峅寺は、稲荷町へと向かう
不二越・上滝線との小さな接続駅です。
不二越・上滝線の乗車記はこちらです。
時刻は16:40。
西日が丁度、駅舎に隠れようと
しているところでした。
岩峅寺を過ぎると、のどかな田園風景から一変し
常願寺川の作る山間を走りました。
山間の小駅、横江駅です。
朽ちかけたような小さな待合室が
あるばかりの無人駅でした。
横江を過ぎると、谷が深くなり渓谷沿いとなります。
13年前、深い雪の中、初めてこの立山線に乗ったときは
之ほど深い渓谷を走る路線とは気がつきませんでした。
雨模様だった天気が、急速に回復していた為か
常願寺川の川面から水蒸気が湧き上がり、
幻想的な景色が広がってきました。
千垣駅を過ぎると立山線の線路は
常願寺川を渡っていきます。
川の両側の切り立った崖。
電車は、最徐行してこの鉄橋を渡り
常願寺川の眺めを存分に楽しませてくれました。
常願寺川を渡った有峰口を過ぎ、
再び、常願寺川沿いに走りました。
農家の向こうにも川面から
沸き立つ水蒸気が見えていました。
夕暮れの山間の集落の景色が
心に沁みました。
夕暮れの本宮駅です。
寂れた駅舎に明りが灯っていました。
本宮を過ぎると、荒々しい石で
埋め尽くされた常願寺川の
流れが見えてきました。
谷がいよいよ深くなり、
周囲も暗くなりかけた頃
定刻に終着の立山に着きました、
改札口の様子です。
がっしりとしたコンクリート製の駅舎の内部で、
すでに真夜中の様な感じです。
数少ない乗客が去り、
ひっそりとした立山駅の様子です。
この立山駅は立山黒部アルペンルートの入り口で、
春から秋にかけて、立山駅からはケーブル・カーが
美女平まで接続しており、さらに美女平からは
立山・雄山の麓室堂までバスが運行されています。
アルペンルートの乗車記はこちらです。
不二越・上滝線
乗車日:Jan. 30, 1995 & May 30, 2012
不二越・上滝線は富山地方鉄道立山線の岩峅寺から
岩峅寺から南富山までが上滝線、南富山 - 稲荷町間が不二越線ですが、
この不二越・上滝線には1995年と2012年に乗車しています。
1995年に乗車した際の様子は こちらです。
2012年に乗車した際は、魚津城やその周辺を散策した後、
魚津城の登城記はこちらです。
不二越・上滝線の岩峅寺駅のホームは、
(岩峅寺 - 南富山 - 稲荷町)
Fujikoshi, Kamitaki Line
(Iwakuraji - Minami Toyama - Inari Cho)
南富山を経て、本線の稲荷町を結ぶ路線です。
この二つの路線を合わせて不二越・上滝線の通称で呼ばれているようで、
稲荷町- 岩峅寺まで立山線のバイパスルート的な位置関係になっています。
ここでは、2012年に乗車した際の記事を紹介します。
富山に戻る途中に岩峅寺まで寄り道をして乗車しました。
立山線のホームとは少し離れた所にありました。
夕刻近くの富山方面行の電車は車内は空いていました。

撮影: 2012年5月
不二越・上滝線の電車は、午前は一時間に一本、
午後は30分から40分毎に運行されています。
不二越・上滝線の先頭車両からの眺めです。

撮影: 2012年5月
不二越・上滝線は単線です。
岩峅寺を発車すると左へとカーブしていきます。
撮影: 2012年5月
列車はすべて富山 - 岩峅寺間の運行になっています。
周囲はのどかな田園風景でした。
走り出してすぐに大きな川を渡りました。
撮影: 2012年5月
立山連峰から流れ出す常願寺川です。
鉄橋を渡り終えると、トンネルの中に停車駅がありました。

撮影: 2012年5月
大川寺駅です。
トンネルの横には幾つもの横穴が空いています。
不二越・上滝線は常願寺川の造る扇状地を下って行きます。
撮影: 2012年5月
その富山方面の横穴からホームに
出入りする事が出来るようです。
大川寺駅を過ぎると、再びのどかな景色となりました。
そして線名になっている上滝駅に到着しました。

撮影: 2012年5月
乗降客数は2022年のデータでは一日289人。
月岡を出ると、広々とした田圃も見えてきました。

撮影: 2012年5月
1997年の約半分に減少しています。
扇状地は水はけが良く田圃には向かないという事を、
大庄を過ぎ、次の月岡で下り列車と行き違いをしました。


撮影: 2012年5月
社会の授業で習った記憶がありますが、この田圃の
景色は長年の土地改良の賜物でしょうか。
この辺りは林で囲われた屋敷が点在していました。

撮影: 2012年5月
こうした屋敷林の散居村は高岡の南の砺波平野が
この先、開発を過ぎると、住宅が増え、
撮影: 2012年5月
特に知られていますが、この富山平野でも
見られるとは知りませんでした。
小さな駅が連続するようになりました。
下の写真左は布市駅到着の手前の様子です。
上右の写真は、布市の2つ先の上堀駅の様子です。
小杉駅周辺からは沿線に住宅も増え、

撮影: 2012年5月
布市と上堀の間の小杉駅は、富山南高校と富山高等
専門学校に近く、下校中の高校生の姿がありました。
朝菜町を過ぎると南富山に到着しました。
南富山に到着する手前で、路面電車が見えていました。
「軌道線」本線の乗車記はこちらです。

撮影: 2012年5月
南富山では、軌道線の本線との接続駅になっています。
南富山は上滝線と不二越線との終起点にもなっています。
不二越線は、富山市の市街地の東の端を

撮影: 2012年5月
ここで下り列車と交換して、発車しました。
迂回するように走っていきます。
進行左手には住宅地が続いています。
この先、留置線の電車が見えてくると稲荷町です。

撮影: 2012年5月
南富山から2駅目の不二越では帰宅途中の
多くの乗客がホームで待っていました。
15.7kmを31分で走りました。

撮影: 2012年5月
稲荷町駅は、本線との接続駅ですが、
不二越線のホームは本線とは離れた場所にありました。
稲荷町を発車して少し走ったところで、本線と合流しました。
稲荷町からは複線で富山駅に向かいます。
撮影: 2012年5月
当時建設中だった北陸新幹線の高架橋の脇を走りました。
こうして岩峅寺から34分で終点の電鉄富山に到着しました。


撮影: 2012年5月
不二越・上滝線は、南富山で軌道線への乗り入れも
上滝・不二越線乗車記 2011年11月11日up
立山の駅に戻り、富山から来た電車で
撮影: 2012年5月
検討されているようで、今後の変化が楽しみです。
そのまま折り返し、岩峅寺に戻ります。
岩峅寺で下車して、今度は上滝・
不二越線で富山に向かいます。

古風な洒落た感じの岩峅寺の駅舎。
ガラガラの電車を下りて、雪深く人気のない
駅にいると、ちょっと侘しい感じになってきます。
雪が深深と降りしきるホームに佇んでいると、
富山からの電車が到着しました。
墨絵の様な白と黒の世界に、電車の山吹色と
緑の塗色がとても鮮やかでした。
富山地方鉄道のTOPに戻る
軌道線「本線、支線」
(南富山 - 富山駅前 - 大学前)Street Car Line [Main, Branch]
(Minami Toyama - ToyamaEkimae - Daigakumae)
乗車日:July 30, 2006

富山地方鉄道の軌道線は、不二越・上滝線との接続駅の
南富山から富山駅前を経て富山大学前までの6.4kmの路線です。
開業は1913年(大正2年)の事のようです。
最盛期には10.8kmの路線を有していたそうです。

南富山から富山大学前まで運行されていますが、
正式な路線名称としては、本線、支線、
安野屋線そして呉羽線に分かれています。
この区間をいくつかの区間に分けて紹介します。
南富山 - 荒町
南富山駅は、軌道線の本線の起点で、
不二越・上滝線と軌道線との接続駅です。


不二越・上滝線の線路と並行し、
駅舎の脇に軌道線のホームがありました。
不二越・上滝線の乗車記はこちらです。
古びた駅舎に、古参の路面電車は良く似合っています。
今では、南富山から岩瀬浜まで行く富山港線の
斬新な低床連結車両も乗り入れています。

並行する不二越・上滝線の線路に接続することは、
容易に出来そうで、不二越・上滝線から軌道線に
乗り入れるLRT化はそれほど難しくはなさそうです。
乗車した2012年の時点では、南富山からの路面電車は、
終点の富山大学前までの系統と、途中の富山駅前までの
系統が夫々10分毎に運行されていました。
2020年3月に、富山駅北から岩瀬浜までの、以前の
富山ライトレールとの間の富山駅南北接続線が開業した
現在では、南富山から富山大学前行と、富山港線の
岩瀬浜行が交互に運行されているようです。
南富山の軌道線のホームは単線ですが、
発車するとすぐに複線となります。

少しばかり不二越・上滝線の線路と並走しますが、
南富山駅北側の踏切で、左にカーブを切って、
不二越・上滝線の線路を横断する道路に合流しました。
この道は、岩峅寺から不二越・上滝線と
並走し、富山の市街地に至る県道です。
桜橋電車通りという通りの名前になっています。

南富山の次の停留所、大町周辺の様子です。
沿線には、商店と住宅が続いています。
富山駅方面に進むに従い、ビルが増えてきました。
大町から2つ目の小泉停留所周辺の様子です。

小泉町の次の西中野停留所を過ぎると、
道路に従い緩やかに右にカーブしました。

緩やかなカーブのすぐ先に広貫堂前の停留所があります。
広貫堂前からはほぼ真北に向かって走っていきました。
周囲にはビルが建ち並ぶようになり、交通量も増えてきました。
停留所の間隔も狭く、200m程で次の停留所に停まります。
次の上本町停留所を過ぎたあたりの様子です。
アーケードも続き、周辺は繁華街の街並みです。

次の西町の停留所を過ぎると左手から、
富山都心線の単線の線路が合流してきました。


富山都心線は、2009年に開業した新しい路線で、
富山城西側の丸の内から富山の繁華街である
総曲輪の周囲を巡るように走り西町を結んでいます。
路面電車は富山駅を中心に、反時計方向に
周回するように走っています。
「富山都心線」の乗車記はこちらです。
下の写真は、西町 - 荒町間の様子です。

遠くに、富山駅北側の高層ビルが見えています。
2013年5月に、この辺りに中町の停留所が設けられています。
しばらく走ると荒町の停留所に到着しました。

上の写真は、荒町の停留所から
南富山行の電車に乗車した際の様子です。
南富山駅前から11分程の小旅行でした。
荒町 - 丸の内
荒町から丸の内の区間は、富山地方鉄道軌道線の
丁度、富山市街の中心部に位置しています。
荒町から地鉄前ビルまで北上した後、西に進路を取り、
電鉄富山駅・エスタ前の停留場から富山駅を右手に見て
南下し、丸の内に至るほぼU 字状の区間です。

富山大学前行の路面電車はビル街の中を走っていきました。


煉瓦壁の歴史ある外観のビルが停留所名に
なっている富山電気ビルデイングです。
1936年4月に竣工しています。

富山地方鉄道の軌道線は、南富山 - 富山駅前間で
平日の日中5分間隔のフリークエントサービスをしています。
南富山行の路面電車とすれ違い、後続の電車が接近してきました。
地鉄ビル前の停留所を発車すると、左にカーブを切り、
北陸新幹線の線路と並走する広い通りに合流しました。


合流した先の道が富山駅前を通る目抜き通りになります。
富山地方鉄道の本社ビルを過ぎ、駅前の
ショッピングモールの建物が見えてきました。

ショッピングモールの前が電鉄富山駅・エスタ前の停留所です。
以前、南富山発の電車の半数は、ここで折り返し運転おり、
そのため、折り返し用の渡り線があります。

2015年3月に、高架化された富山駅の一階部分に路面電車の
停留所が出来、かつて電鉄富山駅・エスタ前で折り返していた
路面電車は富山駅まで乗り入れる事になりました。
電鉄富山駅・エスタ前を発車するとすぐに富山駅が見えてきました。
高架の駅舎が北陸新幹線で、その奥に、JR高山本線、
あいの風とやま鉄道の駅が併設しています。

富山大学前に向かう路面電車は、富山駅前の
交差点で左に曲がり南へ向かいます。
下の写真は、富山駅から富山大学前方面に
進む電車から眺めた様子です。

写真奥が電鉄富山駅・エスタ前(南富山方面)方面で、
南富山から富山大学に向かう電車は、写真奥から
右側のカーブを進んでいきます。

カーブを曲がると、電車の後方に富山駅が見えていました。
2015年に乗車したのは日曜日でしたが、車内には多くの乗客がいました。
2006年、2012年に乗車した時に比べ、乗客が増えていると感じました。

新富町の停留所を過ぎると、
進行左手に県庁前公園が見えてきました。

県庁前公園を過ぎると松川を渡りました。

松川は富山城の北側の堀跡を流れる川です。
富山城の登城記はこちらです。
松川を渡ると程なく丸の内の停留所に到着しました。

丸の内は、富山大学前に向かう路線と、
富山新都心線の分岐駅になっています。
丸の内 - 富山大学前
丸の内を発車すると、富山大学前に向かう
路面電車は、右にカーブを切っていきます。
新都心線は、分岐して左にカーブを切ります。
下右の写真は、富山大学前から南富山に向かう電車の
最後尾から丸の内の先のカーブを眺めた様子です。
下左の写真は、丸の内を出て左のカーブした
新都心線の最後尾から眺めた様子です。


上左の写真の奥側が富山大学前の方向になります。
その方向を、南富山に向かう電車の最後尾から
眺めた様子が下の写真です。

真っすぐに複線の線路が延びていました。
丸の内の次の諏訪川原の停留所も見えてきました。


2012年5月に乗車した際は、諏訪川原の
停留所の先は単線になっていました。
そして、安野屋の手前で再び複線に戻っていました。

この区間は従来複線区間でしたが、2012年5月に乗車した際は、
その直前まで神通川に架かる富山大橋の架け替え工事で、
暫定的に単線になっていたものともいます。
そして、その先の富山大橋を渡っている時の様子です。


2012年5月、架け替えられたばかりの富山大橋の
軌道は真新しく、まるで新線開業後の様でした。
富山大橋の架かる神通川は、ゆったりと流れていました。
かつては上流の神岡鉱山の廃液に由来するイタイイタイ病が
発生していますが、この川の流れからは想像出来ませんでした。
富山大橋を渡ると「トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前」です。

かつては新富山停留所という名称で、その昔は、
富山地方鉄道射水線との接続駅でした。
射水線は、越ノ潟から新湊へと向かう路線で、
その大部分は廃止になっていますが、越ノ潟からの
路線の一部は現在の万葉線になっています。
万葉線の乗車記はこちらです。
トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前を
発車すると再び単線となりました。

この単線区間も、富山大橋の架け替え工事に伴う
一時的なものだったようで、今では複線区間になっています。

そして、複線の線路が単線になると富山大学前に到着しました。
南富山から6.4km、所要時間は約40分程です。

路面電車の郊外の終着の停留所は、線路が急に
途切れてあっけない感じのところが多いのですが、
この富山大学前の停留所もそんな感じでした。
以前は線路はこの先も続き、呉羽まで繋がっていましたが、
太平洋戦争末期に廃線となっています。
実は、2012年5月に乗車した際は、JR高山本線の
西富山から歩いて富山大学前に向かい、
ここから路面電車に乗車しました。

乗車前に歩道橋の上から路面電車を眺めた様子です。
2012年当時、富山大学工学部方面への延伸の話題が
出ていましたが、その後その件は進展が無いようです。


富山大学前で発車前の様子です。
朝に、大学から都心に向かう乗客は少なく
車内は空いていました。
西富山から富山大学前に向かう途中に立ち寄った
大峪城の登城記はこちらです。
軌道線「富山都心線」
Street Car Line [Toyama Central]
(Marunouchi - Ote Mall - Aramachi)
乗車日:Feb. 11, 2010 & May 31, 2012

コンパクトシティ化を打ち出し、路面電車を中心とする
公共交通機関の充実化を図っている富山市で
2009年12月に新しい路線が開業しています。
新しく開業したのは富山都心線です。
富山地方鉄道軌道線の丸の内で分岐し富山城址公園の
お堀端を走り、国際会議場前から南に向きを変え、
富山の中心部の総曲輪で再び東に向かい
西町近くで軌道線に接続するルートです。
営業キロ数は0.9kmです。

元々1973年までは、丸の内から旅籠町経由で
西町に至る路線が運行されていました。
従って36年ぶりの復活ともいえます。
富山都心線は単線で、荒町 - 富山駅 - 丸の内間の
既存の軌道線と合わせ、反時計方向に
周回する様に運行されています。
また、この富山都心線は、富山市が軌道を保有し
富山地方鉄道が運行する上下分離方式を採用しています。
この富山都心線には、2010年2月に初めて乗車しました。
この日は生憎の雨模様の天気で、その後2012年5月に、
富山に出張の機会が有った際に、再乗しました。
その時の様子を紹介します。
2012年5月31日、大学前行の軌道線の電車に乗り、
丸の内で下車し、都心線の電車を待ちました。

丸の内は、大学前へ向かう複線の軌道線との分岐駅です。
大学前に向かう複線の線路は、停留所を出ると右に
カーブを切り、都心線は左に曲がります。
反時計方向の一方通行なので
左側の線路からしか分岐していません。
しばらく待ってやってきた都心線の電車です。

富山ライトレールと同じ、低床式の連結車です。
富山都心線は、朝は9時前、夜は20:30以降は30分毎、
その間は13〜15分毎に走っています。
乗車したのは朝の9時前の電車です。

まだ繁華街のお店は開いておらず、
次の国際会議場で開催されている
学会の参加者が数人乗っていました。
最後尾に陣取り、去りゆく景色を眺めました。
丸の内を発車した直後の様子です。

発車してすぐに左に曲がり、
富山城址公園の南の通りを走ります。
広い通りの中央に単線の線路が敷かれています。

綺麗に区画整備され、天気がいい事もあって
すっきりとした街という印象でした。
進行方向左手には富山城の天守閣も見えてきました。

富山城の登城記はこちらです。
富山城天守閣の正面に富山国際会議場があり、
その角で右にカーブを切りました。

曲がりきったところが国際会議場前の停留所です。

国際会議場の向かいには航空会社系列の
ホテルの高層ビルもあり賑わった雰囲気です。
この通りをしばらく南に走ったところで
大手モール停留場に到着しました。

この大手モールの停留所を発車すると、すぐに
左にカーブし、再び東に向かって走りました。

この通りは車の交通量が多く、路面電車と
並走する車線は渋滞していました。


この界隈は総曲輪と呼ばれる富山で随一の繁華街です。
富山城の外堀を埋め立てたところで、明治に入り
本願寺の別院の参拝客で賑わった所だそうです。
しかし、近年は百貨店が閉店するなど、
往時の賑わいは陰りをみせてきたようです。
その後、総曲輪通り商店街に面してグランドプラザや
総曲輪フェリオなどの商業施設が建てられていますが、
この富山都心線の開業で更に多くの人が
総曲輪に出掛けられるようになるといいなと思います。
グランドプラザ前の停留所を発車すると西町の
交差点で左に曲がり軌道線の本線に合流します。

合流してすぐに西町停留所の南行の乗降場がありますが
北行きの乗降場は、合流地点の手前にあるので、
次の停留場は荒町になります。


荒町の停留所で富山都心線の
電車を下車し、発車を見送った様子です。
丸の内停留所から約10分の旅です。
ちなみに富山地方鉄道は、2013年5月17日に
西町と荒町間に中町停留所を設けてます。
北行きのみの乗降場ですが、富山都心線で
中町で下車し、西町で軌道線の南行き電車へ
乗り換える事が出来、便利になっています。
|
|
|
|