|
|
|
|
JR東海 関西本線
(名古屋 - 亀山)
JR Central, Kansai Main Line


撮影: 2012年1月
関西本線は名古屋から四日市、亀山、奈良を経由し、
大阪のJR難波に至る174.9kmの路線です。
JR発足後は、名古屋 - 亀山間がJR東海によって、
亀山 - JR難波間がJR西日本によって運営されています。
名古屋と大阪の近郊区間になっている、名古屋 - 亀山・
加茂 - 奈良 - JR難波間は電化されていますが、
中間の関 - 加茂間は未電化区間です。
このページではJR東海の運営する
名古屋 - 亀山間を紹介します。
JR西日本の関西本線の乗車記はこちらです。
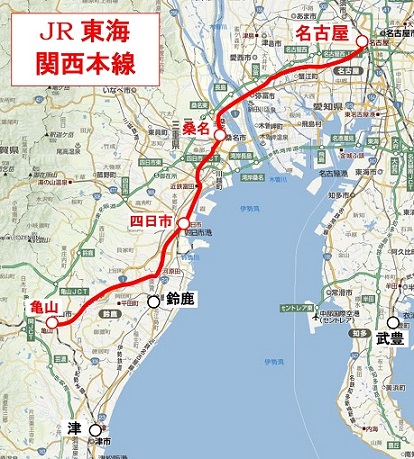
Yahoo地図に追記
関西本線の歴史は、1888年(明治21年)に大阪鉄道が
湊町(現:JR難波) - 柏原間を開通させた事でスタートしています。
大阪鉄道は1892年(明治25年)に奈良までの路線を開業しています。
1890年(明治23年)には関西鉄道が、奈良以東の路線を開業させ、
1899年(明治32年)に名古屋 - 奈良間が開通しました。
翌1900年(明治33年)には、大阪鉄道が関西鉄道に路線を譲渡し、
名古屋 - 湊町間が関西鉄道の路線として運営されるようになりました。
1907年(明治40年)に関西鉄道が国有化され、
1987年(昭和62年)にはJR化され、亀山以東がJR東海、
亀山以西がJR西日本の路線になっています。
JR東海が運営する事になった名古屋 - 亀山間は、国鉄時代には、
未電化で、運転本数も少なく、客車列車も走るような路線でしたが、
JR化後は運転本数も増え、伊勢鉄道経由で鳥羽行の快速「みえ」や
亀山行の快速も毎時一往復づつ走るようになりました。
快速「みえ」の乗車記はこちらです。
その関西本線の名古屋 - 亀山間は、何度も乗ったことがあります。
2010年10月に乗車した際の様子を中心に紹介しようと思います。
名古屋 - 桑名
Nagoya - Kuwana
Sep. 24, '16
桑名 - 四日市
Kuwana - Yokkaichi
Sep. 30, '16
四日市 - 亀山
Yokkaichi - Kameyama
NEW! Oct. 04, '16
関西本線のTOPに戻る JR編に戻る
|
|
|
|
名古屋 - 桑名
(Nagoya - Kuwana)

名古屋駅の関西本線のホームは、
新幹線に最も近い12番線と13番線になっています。

撮影: 2012年3月
13番線に停車中の四日市行の普通電車です。
ホーム反対側は特急「ワイドビュー南紀」や
快速「みえ」が発着する12番線です。

撮影: 2010年10月
2010年10月に乗車した際にも、快速「みえ」を
待つ乗客が長い列を作っていました。
快速「みえ」の乗車記はこちらです。
2010年10月、7:40発の普通列車に乗車しました。
関西本線は、名古屋を発車すると、
すぐに新幹線をアンダークロスします。

撮影: 2015年2月
東海道本線と中央西線の線路も左に分かれていきました。
中央西線の乗車記はこちらです。
その先で、あおなみ線の線路もアンダークロスし、
再開発された笹島地区を進んでいきます。
あおなみ線の乗車記はこちらです。

撮影: 2010年10月
振り返ると、名古屋駅前の高層ビルが
建ち並んでいました。
あおなみ線のささしまライブ駅を過ぎると、
進行右手に車両基地が広がります。


撮影: 2010年10月
この車両基地には、JR東海の看板列車の特急「ワイドビューひだ」や
特急「ワイドビュー南紀」用のキハ85系の車両が停車していました。
この先のJR東海名古屋工場を過ぎると、
複線だった関西本線は単線となりました。
進行右手から近鉄の線路がより沿ってきます。

撮影: 2010年10月
丁度、アーバンライナーが走り去っていきました。
左手にはあおなみ線の電車も走っています。
この辺りは鉄道路線が集中しているので、
車窓風景が楽しい区間です。
地平から勾配を上ると、左手を走っていたあおなみ線は
左にカーブを切り関西線と分かれていきます。
関西本線は右にカーブを切り、八田駅に到着しました。

撮影: 2010年10月
八田駅は地下鉄東山線と近鉄名古屋線との接続駅です。
2002年に高架化されていますが、その際に500m東側に
駅の場所が移り、他路線との乗り換えが便利になっています。
名古屋から八田までの区間の前面展望の動画です:
撮影: 2012年3月
八田を発車すると地平に下り、近鉄をアンダークロスしました。

撮影: 2010年10月
近鉄名古屋線は、名古屋 - 四日市間で概ね関西本線と
並走していますが、ここから弥冨までの区間は、
1 〜 2km程、JRの南側を走る様になります。
近鉄をアンダークロスすると、庄内川と
新川の鉄橋を続けて渡りました。

撮影: 2010年10月
名古屋の西側は、濃尾平野の低湿地が続き
ゼロメートル地帯が広がっています。
新川を越えると、新しい住宅が増え、マンションや
高層団地も車窓から見えるようになり、
春日駅に到着しました。
八田 - 春日間の前面展望の動画です:
撮影: 2012年3月
春日駅は2001年に開業した新しい駅ですが、
周囲にこうしたアパートや住宅があるため、名古屋と
桑名の間の駅では、最も利用客の多い駅になっています。

撮影: 2012年3月
春日を発車すると、平地に住宅地が広がる光景になりました。

撮影: 2012年3月
春日の次の駅が蟹江です。

撮影: 2012年3月
2012年3月に乗車した際には、
ここで快速「みえ」と交換しました。
名古屋地区の関西本線は、鳥羽へ向かう快速「みえ」と
亀山行きの快速、そして四日市の普通列車が2本と
一時間に4本の列車が走っています。
しかし、名古屋から弥富までは単線区間が続く為、
頻繁に列車の交換があります。
蟹江から次の永和に向かう線路の様子です。

撮影: 2010年10月
単線ですが、複線用の土地は確保されています。
この区間の関西本線の線路容量は限界にきている様にも
思えるので、早く複線化されないか、といつも思います。
列車は日光川を渡りました。


撮影: 2012年3月
まるで水郷地帯のような眺めです。
次の永和では亀山からの快速電車の通過待ちでした。

撮影: 2012年3月
広い濃尾平野を走っているので、
ずっと平地が続いています。
遠くに高速道路が見えて来ました。

撮影: 2010年10月
田圃の中、複線になったと思ったら、
電車が停車しました。
ここは白鳥という名前の信号場です。

撮影: 2010年10月
2010年10月に乗車した際には、この白鳥信号場に
停車中に、快速「みえ51号」が先行していきました。
白鳥信号場から住宅が増え、到着したのは弥富駅です。
弥富駅は名鉄尾西線との乗換駅です。
 撮影: 2010年10月 |
 撮影: 2012年3月 |
弥富駅に発着する列車は、JR・名鉄とも一時間に2本ですが、
接続は考慮されておらずJRの列車に乗っていて、
名鉄の車両を見る機会はそれ程多くはありません。
この弥富駅は海抜マイナス0.93mの位置にあり、
地上駅としては日本で最も低い駅になっています。
弥富を発車すると関西本線は立派な
複線となり、木曽川橋梁を渡ります。

撮影: 2010年10月
愛知県と三重県の県境を越え、鉄橋を渡り終えると、
木曽川と長良川に挟まれた長島に入ります。
周囲を堤防で囲われた輪中の地です。
弥富 - 長島間の前面展望の動画です:
撮影: 2012年3月
長島で行違った名古屋行きの普通電車です。

撮影: 2012年3月
長島を発車し、再び勾配を上り
長良川の鉄橋へと向かいました。

撮影: 2012年3月
車窓から眺める輪中の景色です。
以前は、堤防に沿って集落が形成されていたそうですが
今では、平地にも住宅地が広がっています。
車窓から眺める輪中の景色です。
以前は、堤防に沿って集落が形成されていたそうですが
今では、平地にも住宅地が広がっています。
揖斐・長良川橋梁を渡りました。
近鉄の揖斐・長良橋梁が並走し、
その向こうに長良川河口堰も見えています。
 撮影: 2010年10月 |
 撮影: 2012年3月 |
長良川に続き、堤防で長良川と隔てられた
揖斐川も渡っていきます。
木曽川も合わせ、川幅いっぱいに水を湛えて流れる
この三つの川はいかにも大河といった感じがします。
揖斐・長良橋梁を渡りえ終えると
関西線は大きく左にカーブを切りました。

撮影: 2010年10月
この区間の動画は、こちらです:
撮影: 2012年3月
進行方向左手を走っていた近鉄名古屋線が
右側に移ると、次の桑名ももうすぐです。

撮影: 2010年10月
桑名 - 四日市
(Kuwana - Yokkaichi)

名古屋から33分で桑名に到着しました。
桑名は名古屋 - 四日市駅間で最も乗降客の多い駅です。

撮影: 2012年3月
国鉄時代には、殆どの乗客が近鉄を利用していたと思いますが、
国鉄末期に、名古屋 - 桑名間には特定区間運賃が適用され
JRになって以降、消費税改定以外に運賃値上げがなかった為、
この区間の運賃はJRの方が90円安くなり、運転本数が
増えた事もあって、JRを利用する人も増えたようです。
桑名は、養老鉄道と三岐鉄道北勢線との接続駅です。
発車した後、進行左手に北勢線の電車が見えました。

撮影: 2010年10月
近鉄名古屋線は軌間が1,435mmの標準軌、JRと養老鉄道が
1,067mmの狭軌、そして北勢線の軌間は762mmの特殊狭軌です。
こうした3つの軌間の異なる路線が集まっている駅は、
日本の中では、桑名駅だけだと思います。
世界的にも珍しいのではないでしょうか。
三岐鉄道北勢線の乗車記はこちらです。
桑名を発車すると単線となり、先ほど
眺めた北勢線をアンダークロスしました。

撮影: 2010年10月
北勢線の鉄橋や橋桁は、いかにも心細い造りです。
この橋桁を過ぎると、関西本線は再び複線になります。
北勢線の鉄橋を掛けかえれば、単線区間を解消する
事が出来ますが、その計画はないように思います。
複線となり、しばらく走ったところで、
上り電車とすれ違いました。

撮影: 2010年10月
この先で、近鉄をアンダークロスしていきます。
この辺りは直線的な線路配置が続き、
関西本線の電車もスピードを上げて走ります。

撮影: 2010年10月
緩やかな丘陵地を抜け、朝日を過ぎ、
田圃が広がる景色となりました。
朝明川を渡ると、関西線は3つの鉄橋を
次々とアンダークロスしていきます。
最初と二つ目の鉄橋が三岐鉄道三岐線、
最後の一つが近鉄名古屋線の鉄橋です。



撮影: 2010年10月
この辺りの関西本線、三岐鉄道、そして
近鉄名古屋線の線路配置は少々複雑です。
西側(進行右手)から近づいてきた三岐鉄道・
三岐線の線路がまずは、JR関西本線を跨ぎます。
一旦、関西本線を跨いだ三岐線の線路が、
再びJR関西本線を跨いで西側に移り、最後に
近鉄名古屋線が、関西本線を横断するように
オーバークロスするという線路配置です。
三岐鉄道三岐線は、元々は関西本線の富田駅に
乗り入れていたのですが、運転本数が少なく、不便な
関西本線を諦め近鉄富田駅に乗り入れる様になっています。
このため、関西本線を二回も跨ぐ線路配置になっていますが、
一つ目と二つ目の鉄橋の間で、貨物線が分岐していて、
近鉄をくぐる際には、その貨物線と関西本線が並走しています。
上右の写真、鉄橋をくぐる一番左の線路がその貨物線です。
三岐線は終点の2駅手前の東藤原駅と愛知県の衣浦臨海鉄道との間で
貨物列車が運行されていて、この貨物線は今も現役です。
三岐鉄道三岐線の乗車記はこちらです。
こうして富田駅に到着しました。
四日市市北部の住宅も密集している地区ですが
多くの人が、近くの近鉄富田駅を利用する為、
関西本線の富田駅はひっそりとしています。
富田の町の散策記はこちらです。


撮影: 2010年10月
富田駅に停車中の亀山行の普通電車です。
この富田で、上り列車との行き違いです。
反対側のホームには貨物列車も停車していました。
桑名の先の北勢線のガードをアンダークロスしてから富田までは
複線でしたが、富田を出ると単線となり住宅地の間を抜けていきます。

撮影: 2010年10月
国道一号線のガードを潜り、
しばらく走ると富田浜に到着です。
2012年1月に、この富田浜から関西本線の
電車に乗る機会がありました。


撮影: 2012年1月
この富田浜も乗降客が少なく、一日僅か179人で、
駅員のいない無人駅になっています。
撮影: 2012年1月
2012年1月に乗車した際、到着した
四日市駅行きの電車の様子です。
日中、富田浜駅に到着するのは、
1時間に2本の四日市行の普通のみです。
富田浜を発車すると、景色が開け、
進行左手には、コンビナート群が見えてきます。

撮影: 2012年1月
コンビナートの手前に、大阪万博の際の
オーストラリア館だった建物が見えていました。

撮影: 2012年1月
四日市は、1960年代に深刻な公害の被害がありました。
四日市喘息の被害の中心は南部の塩浜地区でしたが、
この富田周辺では重油による魚の汚染が発生したようです。
コンビナートを眺めるうちに、三滝川を渡り、
引き込み線が寄り添っていました。

撮影: 2010年10月
四日市駅も、もうすぐです。
富田浜 - 四日市間の前面車窓風景の様子です。
撮影: 2012年1月
この区間は、再び複線になっています。
四日市に到着した普通電車です。

撮影: 2012年1月
2012年1月に乗車した際には、
この四日市で、亀山行に乗り換えました。
その待ち時間の間に、上りの特急
「ワイドビュー南紀」が到着しました。
撮影: 2012年1月
「ワイドビュー南紀」は名古屋と紀伊勝浦を結ぶ観光特急です。
一日に定期列車は4往復と本数も限られていますが、
四日市から終点の名古屋に向かう列車に
乗り込む人がいたのはちょっと驚きました。
四日市 - 亀山
(Yokkaichi - Kameyama)

四日市は、名古屋との結びつきが強く、
三重県最大の都市です。
四日市の散策記はこちらです。
本来であればこの関西本線も乗客で
溢れていても不思議ではありませんが、
あまり活気がありません。
四日市駅の東に広がる貨物の
留置場と工業地帯の様子です。

撮影: 2012年1月
以前は、この四日市駅が中心駅で、近鉄名古屋線も
駅前まで乗り入れていましたが、街の中心が西側に移り、
近鉄は線路配置を変え、繁華街に駅を設置しています。

Wikipediaより借用しています
今では、利便性なども含め、名古屋 - 四日市間の
競争では全くといっていい程、勝負にはなっていません。
四日市を発車すると亀山方面のホームの端に
伊勢鉄道の列車が停まっていました。

撮影: 2010年10月
伊勢鉄道は、関西本線の河原田で分岐し、津へと向かう鉄道です。
名古屋からの特急「ワイドビュー南紀」や、鳥羽や伊勢に向かう
快速「みえ」もこの路線を走りますが、国鉄民営化の際に
何故か第三セクターの運営する路線になっています。
「ワイドビュー南紀」が一日4往復、快速「みえ」が
毎時一本走るほか、先ほどのレールバスが
毎時一本程、四日市と津の間を結んでいます。
側線が寄り添い、また工業地帯へと向かう
貨物の枝線が分岐していきました。


撮影: 2010年10月
この先で近鉄名古屋線のガードをくぐります。

撮影: 2010年10月
進行左手には、再びコンビナートが見えています。
塩浜地区のコンビナートです。


撮影: 2012年1月
コンビナートの景色を眺めるうちに南四日市駅となり、
ここからは複線になりました。

撮影: 2010年10月
この複線区間で、快速「みえ」とすれ違いました。
快速「みえ」の乗車記はこちらです。
この先で内部川を渡ると、複線の線路間隔が
広がり、その内側に分岐していきました。


撮影: 2010年10月
真っすぐに進む線路が伊勢鉄道の線路で、
このまま複線で鈴鹿方面に向かいます。
関西本線の名古屋地区の実態は、名古屋 から
特急「ワイドビュー南紀」や快速「みえ」も走る
伊勢鉄道経由で津や松阪に向かう線路が本線で、
ここから亀山に向かう路線は支線の様です。
内側に分岐した関西線の線路は上下線が合流し
単線となって河原田駅に向かいました。

撮影: 2010年10月
地平にある関西本線の河原田駅です。
伊勢鉄道の駅は、左手の高架上にあります。
河原田駅から関西本線は鈴鹿川に沿うように
西へと向かっていきます。

撮影: 2010年10月
のどかな景色が広がります。
次の河曲(かわの)駅の北側は、
伊勢国分寺があったところとされています。
次の加佐登で、上り電車と交換しました。


撮影: 2010年10月
この辺りも、とてものどかなところです。
日本武尊の終焉の地とされていますが、
その事はあまり知られていないようです。
のどかな加佐登駅ですが、かつては
鈴鹿市の代表駅になっていた事がありました。
次の井田川も、小さな無人駅です。

撮影: 2010年10月
井田川を発車し、田圃が広がる景色の中、
やがて右に大きくカーブを切り、線路が
いくつも分岐するようになると亀山です。

撮影: 2010年10月
車窓左手から紀勢本線が合流するのですが、
駅の構内が広く、また合流するのが駅の直前なので
その線路を見つけるのは、なかなか容易ではありません。

撮影: 2010年10月
こうして亀山に到着した電車です。
日中の快速運転している時間帯で、名古屋から59.9kmの
距離を、1時間5分程、朝夕は、1時間20分程の所要時間です。
亀山駅の様子です。


撮影: 2012年1月
一時は液晶TVの生産基地として、「世界の亀山」
とまで称されましたが、駅はひっそりとしていました。
亀山には江戸時代に亀山藩が置かれていました。
亀山城の登城記はこちらです。
城下町・亀山の散策記はこちらです。
亀山は、JR東海とJR西日本との接続駅です。
奈良方面に向かうには、JR西日本の列車に
乗り換えになります。
JR西日本の関西本線の乗車記はこちらです。