Old Road to Ashigara Summit


足柄古道は、奈良時代から平安時代にかけ、
箱根を超える街道として整備された路です。
静岡県のJR足柄駅から足柄峠を通り、
大雄山駅とを、ほぼ東西に結んでいます。
足柄峠からは富士山が一望出来るという事もあり、
2011年12月に、足柄古道を辿り足柄峠を目指しました。
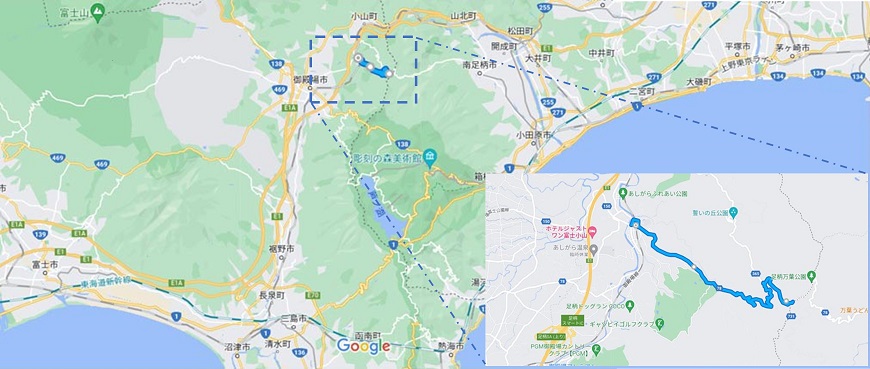
標高330mの足柄駅から標高759mの足柄峠まで
標高差429m、約5.5kmの道のりを
1時間40分程で上りました。
足柄峠の散策記は こちらです。 足柄駅から水飲沢
前日は三島に出張があり、その翌朝に三島から
下土狩までタクシーに乗り、下土狩7:00の
列車に乗り、足柄には7:48に到着しました。

撮影: 2011年12月
足柄駅から足柄峠を目指します。
西側の駅の改札から踏切を越えて
東へ向かいました。

撮影: 2011年12月
振り返ると遠くに富士山が見えていました。
この日は良く晴れ、山頂も綺麗に見えていました。
踏切を渡り、最初の交差点を右に折れました。
標識では、クランク状に左側の道を東に向かうと
足柄古道と案内が出ていますが、地図で見ると
この道は途中で消えていたので別の道を進みました。

撮影: 2011年12月
先ほどの角の次の角を左に折れました。
馬喰坂という名の急坂が続いています。
この道を進むと足柄峠まで行くことが出来ます。

撮影: 2011年12月
急坂を上り、しばらく歩いたところに
嶽之下神社がありました。

撮影: 2011年12月
古道沿いの神社で、何かしら所縁が
ありそうな神社でしたが、由緒などを
記した案内板はありませんでした。

撮影: 2011年12月
境内からは、富士山が輝くように聳えていました。
五合目辺りに、うっすら雲が掛かっていました。
嶽之下神社から先は集落は無くなり、
雑木林の中を歩くようになります。

撮影: 2011年12月
朝日が木々の間から差し込んできました。
朝日を浴び、雑木林が輝くようでした。

撮影: 2011年11月
雑木林を抜けると、県道との交差点に出ました。


撮影: 2011年12月
この辺りには竹之下一里塚跡がありました。
一里塚が整備されたのは江戸時代に入った
1604年(慶長9年)以降に整備されています。
この路は古くから箱根を超える主要街道でしたが、
箱根路が東海道として整備された後に、
足柄街道と呼ばれるようになったそうです。
この先で振り返って眺めた富士山です。
次第に雲が出てきているのが、
気にかかります。

撮影: 2011年12月
竹之下一里塚跡から10分ほど歩くと、
道が二つに分かれていました。
足柄峠へと向かう車道は左の道を進みますが、
右の路の先に石碑がありました。


撮影: 2011年12月
この石碑は、栗の木沢題目碑といい、日蓮上人が
1274年(文永11年)に身延山に入山する途中、
また1282年(弘安5年)に池上本門寺に向かう際に
竹之下に泊まり、御本尊を書き残したそうです。
このご縁により、地元の人が1862年(文久2年)に、
この地に題目碑を建立し、霊場としたそうです。
身延山の散策記は こちらです。
池上本門寺の散策記は こちらです。
左手の車道を下ると、再び石碑がありました。

撮影: 2011年12月
1839年(天保10年)に建てられたものです。
唯念上人が、飢饉と大疫病に苦しんでいた
足柄の人々を救済するため、念仏を唱えたそうです。
足柄の人々はこれにあやかろうと、南無阿弥陀仏の
名号を彫った碑を建てたと伝わっています。
この先には朽ちかけた案内標識が2つありました。


撮影: 2011年12月
左側は、道路標識で、足柄駅まで2.4km、
足柄峠まで2.5kmと記されていました。
ここがほぼ、中間地点になります。
右の標識は、竹之下合戦の戦ヶ入りの碑でした。
竹之下合戦は、足利尊氏討伐を記した後醍醐天皇の
宣旨を受けた新田義貞と、足利尊氏との間の戦です。
戦は新暦で、1336年(建武2年)1月に生じています。
二つの碑のある辺りは、沢を渡る位置にあり、
車道は一旦下り坂になっていましたが、
再び上り坂となりました。

撮影: 2011年12月
道端に古びた案内板が置かれていました。
「水呑沢」の案内板です。

撮影: 2011年12月
急坂を往来する旅人がこの沢で喉を
潤した為、この地名が付いたそうです。
水飲沢からも上り坂を歩いていきました。
やがて車道の脇に石畳の道が見えてきました。


撮影: 2011年12月
この路は赤坂古道と呼ばれ、
1000年以上も前に開かれた路です。
江戸時代にもこの古道は用いられ、相模国から
甲斐の国に塩を運ぶのに使われた街道のようです。
古道の傍らには古い仏像がありました。
馬頭観音像です。

撮影: 2011年12月
この路で遭難する人も多く、村人が遭難者の供養と
道中安全を願い、1775年(安永3年)に建立したそうです。
赤坂古道は雑木林の中を急こう配の山道が連なっています。

撮影: 2011年12月
行きかう人もなく、少々心細く感じる山道でした。
それでも、古道は踏み固まれていて
道を外す事はありませんでした。


撮影: 2011年12月
足柄駅から出発した際には冷え込んでいましたが、
古道を上るうちに汗ばむようになっています。
かなり足に疲れが来ていますが、帰りの時間が
気になるので、ペースを緩めずに歩いていました。
赤坂古道に分け入って15分ほどすると
やっと視界が開け、後方に富士山が見えました。

撮影: 2011年12月
歩き出した足柄駅では綺麗に見えていましたが、
湧き出した雲が厚くなり、山頂に迫っています。
再び、石畳の道となりました。
勾配は緩くなり、歩きやすい道です。

撮影: 2011年12月
やがて、車道に出ました。
赤坂古道を横切るように車道が造られたようで、
車道を渡った反対側に、古道が続いていました。


撮影: 2011年12月
再び石畳の山道が続いています。
周囲の木々の様子は、先ほどと比べると、
心なしか鬱蒼とした感じが少なくなって来ました。

撮影: 2011年12月
先ほどの車道から5分程で再び車道に出ました。


撮影: 2011年12月
ここからはこの車道に沿って歩いていきました。
この車道に沿ってはいくつもの碑がありました。
下の写真は、車道から一段高い所にあった芭蕉の句碑です。

撮影: 2011年12月
"目にかかる 時やことさら 五月富士"
案内板によると、この句は芭蕉が亡くなった
1694年(元禄7年)夏に詠まれたそうです。
この年の夏、芭蕉は江戸を発ち大坂に向かっています。
芭蕉が最後に眺めた富士の様子を詠んだ句なのでしょうか。
芭蕉は、この旅で向かった大坂で亡くなっています。
この先には六地蔵が二箇所ありました。


撮影: 2011年12月
振り返って眺める富士山は、生憎、
雲が頂上を覆ってしまっていました。

撮影: 2011年12月
そしてこちらは造林記念碑です。
元々は高台にある足柄城二の丸にあった碑を
1986年にこの地に移転したそうです。

撮影: 2011年12月
実は、その碑の事よりも、この碑の案内板に、
この碑の現在地が、足柄城の西の出丸という
事が記載されていて、興味を惹きました。
富士山の東側にある三国山の姿も見えていました。
三国山は、駿河、甲斐そして武蔵の三ヵ国の国境です。

撮影: 2011年12月
こちらは、謂れは分りませんが、一切経宝塔です。

撮影: 2011年12月
一切経宝塔の先では、車道の東側に
高い擁壁が続くようになります。


撮影: 2011年12月
この擁壁の上が、足柄城址です。
ここから足柄峠は目と鼻の先です。
麓の足柄駅から約1時間半かけて到着しました。
足柄峠の散策記は こちらです。
足柄城の登城記はこちらです。 中部のページに戻る Shane旅日記 日本編に戻る